きみとなら どこへでも行ける。
きみとなら どこへでも行きたい。
たとえその道が 砂利道でも 雑草だらけでも。
きみと手を繋いでいれば どこへでも行ける。
“そこ”に 何も無くても
“そこ”から 二度と戻れなくなっても
それでもいい。
きみと手を繋いで どこへでも行こう。
+++
911番踏みの冬月さんから無理矢理貰ったお題『冒険』消化です。
なんだか物凄い日生解釈の詩になってしまいました;;
ライオンを撮りにサバンナロケに行くような詩じゃなくてスミマセン(笑)。
きみが泣いた。
僕は笑った。
そしたらきみは怒って。
僕は、それでも笑った。
そしたらきみは、ようやく笑顔になって。
僕はしあわせになった。
きみにはたくさん笑っていてほしいです。
きみの涙を笑顔に変えるのは、できれば僕にさせてほしいです。
そんな気持ち。
あまりに放置しすぎて、しかもカウンタが予想外にまわっていたので、ちょっと焦ってます。
こんなサイトに足を運んでくださってありがとうございます。
スミマセン;
そろそろ復帰しようと思うのですが、せっかく何日分も空いているので、
一気に長編小説アップしてしまいます。(て言っても原稿用紙60枚ちょいです;)
新しい日から古い日に遡っていきます。
携帯で読んでる方は今回読まないで下さいネ;
パケ死確実ですから;;
一昨年に唯一書いたある程度文章量のあるもの。
一昨年は最高に書き物してませんでした(汗)。
リハビリもかねてのんびり書いていたものなので、正直レベルは低いです;
投稿するために書いてたんですが、やめときました(苦笑)。
原稿用紙用に書いたものなので改行少なくて読みにくいかもしれません。
究極に暇な時に、暇つぶしに読んで頂ければ幸い。
ちなみに手を加えてないどころか、読み返してもいません(切腹)。
ガタガタ。
去年は二次創作をひたすらやったので、今年は投稿できるようなものを書きたいなぁ、、、とか。
が…頑張りマス;
+ジョマク+
きみが目を開いたらそこは真っ白で、無限の空間に思えた。
きみが声を出そうと思っても、かすれて声は出てこない。
ひとりぼっちの、淋しい空間。
そこできみは、何を求める?
隣で眠ってくれる人?
それとも、何もしてくれない神サマ……?
ぼくには、居て欲しい人が居ない。
ぼくには、誰も求めることなんか、――できやしないのだ。
シャボン玉。
ほのかに七色に光る、透明な球体。
空気にさらされて、皮膜がだんだん薄くなる。
そして弾けて……消えてしまう。
そう。
そんな感じだった。
ぼくたちは所詮、透明の球体。たくさんのシャボン玉達に雑ざって生まれ、いつしか簡単に弾けてしまうのだ。
数が多すぎて、目立ちはしない。
世の中の矛盾が僕の周りには溢れ、僕の存在価値など、たやすく消えてしまうだろう。
否、『ソンナモノ』なんか、存在しないのかもしれない。
ぼくたちは突然、見知らぬ空間に放り込まれる。
********
『Lシティ』
高き知力を誇る人間により構成され、より高きを目指す街。
――ラーニングシティ。
********
+イチ+
「ヒダカ! ヒダカ!」
僕の名前が、宙を漂った。
ここは『ガッコウ』で、それは僕が一番馬鹿にしている連中が集う場所だ。
ガッコウと云うのは、一定の『ニンゲン』を育てるために存在する。特に、ここはそうだ。IQばかりが高くて、EQはきっと低い。
僕も所詮はその中の一人で、友人など一人も居ない。
……否、それは少し前までの話。
今はサキヤと云う友人が居て、何故か、ガッコウに対する冷たい感情も変化しているような気がする。
うちのガッコウは全て定期的に試験を行い、その結果でクラスを編成している。そして僕は今2クラス。サキヤは1クラスだ。
昔1クラスから2クラスにクラス落ちした時はそうとう腹が立ったが、結局そんな風に考える自分にも、今では腹が立つ。
とにかく、僕はここが大嫌いだ。
「ヒダカ!」
もう一度名を呼ばれて。
「……はい」
僕はようやく返事をした。
担任のミカゲだった。
「お前、志望校調査、出してないな」
「……はぁ」
進路調査。
僕は中等二年で、世間的には高校受験を気にする時期だろう。
が、高等へはこのまま持ち上がりで『この街』の高等学校に進学することに決められている。
故に、僕たちは大学受験生だ。
「タダイマ」
形式的な挨拶だけを玄関に残し、僕はさっさと階段を上がる。
どうせ、誰も居やしない。
自室ですぐに鞄を開き、制服のまま宿題を始める。
数学のプリント十枚。
英語のプリント四枚。
経済学のプリント二枚。
国語のプリント八枚。
黙々と鉛筆を走らせて。僕は、学習内容を叩き込む。
「ヒダカ」
ふと部屋のドアが開いた。母親が立っている。
「夕飯よ」
にこりともしない表情で、僕に用件を伝える。彼女は仕事から帰ってきたばかりのようで、まだ灰色のスーツに身を包んでいた。
乱れの無い、ウェーブのかかった毛先。
今日も栄養管理課に配給された夕食に違いない。
「うん。後で」
すぐに視線をプリントに戻すと、母親もすぐにドアを閉めた。ばたりと云う、閉鎖的な音。
勉強が大事だから。
学長……管理者の期待に添わねばならないから。
――この街、『Lシティ』に生まれてきた者、『Lヒューマン』の、ツトメだから。
……でも僕は、別の感情が存在することを知ってしまった。
「ヒダカ」
聞こえてきた声は、母親じゃなくて。
「サキヤ……」
電源を入れているパソコンの通信画面に映し出された、唯一の友人の声だった。
通信オンに切り替える。
「サキヤ?」
「ヒダカ? ごめん、勉強中だったの?」
「サキヤは? 終わった?」
「ううん、まだ。休憩中だよ」
休憩。
確かに適度な休憩は学習に良い影響を与えると言われるけれど。でも、それを上手く摂ることが出来ない。抵抗を感じる。
抵抗なく休憩を取り入れられるのは、やはりサキヤが『外』の人間だからだろうか。
『外』
このLシティでは、元々ここで生まれ育った者以外にも時折ニンゲンを補充している。
――優秀なニンゲン。
――この町に必要なニンゲン。
サキヤは四年前、管理官に認められて編入してきた。
「ヒダカはちゃんと休憩した? 夕食は食べた?」
心配そうに質問を続けるサキヤに、僕は黙り込んだまま小さく首を横に振った。
スピーカーから、「やっぱり」と小さな溜息が聞こえる。
「駄目だよ、休憩しなきゃ。夕食もちゃんと食べないと」
サキヤに言われると、何故か嫌な気がしない。押し付けがましく言ってくる親や、形式的に言ってくる管理官とは違う。
「……うん」
「今日の夕食は何?」
「多分、配給の食事」
「そっか。今日のは味も良かったよ。ほら、食べておいでよ」
外からの人間のサキヤは、いつも配給の食事を食べている。作ってくれる親が居ない。
「……解った」
「じゃあね。適当な時間でちゃんと寝るんだよ? ……また明日」
「うん」
プチ。
小さな音を立てて、通信が切断されたことを知らせる。画面が元の辞書機能に戻った。
制服を脱いで、私服に着替える。
階段を降りると、母親が夕食の並んだ食卓に黙って座っていた。
+ニ+
ガッコウで参考書を見ながら配給のゼリー状ドリンクを飲んでいたら、音もなくサキヤが近付いて来て、両方取り上げられてしまった。
「ヒダカ……こんなもので身体を保つなんて間違ってるよ。何回同じこと言えば解るの」
サキヤはもうほとんど中身の無いドリンクのパックをギュッと握りつぶし、教室の隅に設置されたダストシュートに捨てる。
「あ……」
僕の、朝食。
あれを飲まないと逆に不健康だ……、と困った瞬間ぐいっとサキヤに手を引かれ、廊下に連れて行かれた。
「サキヤ?」
「まだ始業まで時間あるでしょ。食堂、行くよ」
確かに時間は有るけれど。
「でも」
「勉強は後でいいから」
すっかり見破られてしまった。
「……ヒダカの身体の方が先だよ。ヒダカ、優先順位間違えてない?」
少し怒ったような表情をして見せられる。
「……」
サキヤの言うことは、僕には時々よく解らない。でも、不思議と厭な気分にはならないのだ。
食堂に入ったサキヤと僕は、IDカードを見せて注文した。
僕の注文をしたのは、サキヤだけれど。
「ちゃんと噛んで食べるんだよ? 栄養を摂るだけが食事じゃないんだから」
人のまばらな食堂で、サキヤにあれこれ言われながら食事を進める。
冷たい冬。
外は吹き付ける風で寒いだろうが、ガッコウ内はいつも一定の温度に保たれていて快適だ。
施設から施設へ移動するのにも大抵地下道などが設置されているお陰で、それほどまでには寒く無い。
これが当たり前の生活。
両親が生まれたときからすでに習慣付いている、日常。
むろん僕も例外ではなく、逆に外の生活の方が未知だ。
「サキヤ、外の時、どんな生活してた?」
突然駆られた、欲求。思わず口に出してしまう。
知りたい。外のこと、サキヤのこと。
サキヤはにっこりと、でも淋しそうに笑って首を振った。
「……忘れたよ。忘れることにした」
その表情に、僕はスプンをぎゅっと握り締める。
「どうして?」
「思い出したって、仕方がないから。両親はお金と引き換えに、ぼくを……手放したんだから」
今はここにぼくの生活があるよ? と、小さな声で添える。
「サキヤ……」
それが悲しいことなのだと云うことは、なんとなく解った。
でも、たった今自分の中に芽生えた感情を、何と呼んでいいのかが解らない。誰に抱いた感情なのかさえ。
軽蔑……とは、多分違う。
まだ、味わったことの無い感情?
……否、多分有るような気がする。――誰だろう。
「でもやっぱり、恨んでないって言ったら、少し嘘になるな」
「……あ…」
そうか。
管理官だ。
「ヒダカ?」
僕の反応に、サキヤは不思議そうに首をかしげた。顔を覗き込んできて、また不思議そうにする。
恨み。
復讐してやりたいって、思う気持ち。
壊してやりたいって、衝動。
感情の正体に、今まで気付くことが出来なかったけれど、これはきっと、僕が昔から抱いていた感情に違いない。
ここ以外の生活なんて、ほとんど知りやしない。
――でも、本能的に違うと感じている? でも、ここの生活があるのは管理管のお陰。
ましてやサキヤの両親なんて、もっと知らない。
――でも、サキヤに辛い思いをさせるなんて、許せない。でも、その人たちが居なかったら、サキヤはここに存在しない。
食事の手を止めたまま沈黙していると、サキヤがぐいっと水を飲み干して言った。
「親のことなんか、思い出したくも無い。ただちょっと勉強が出来るくらいでこんな生活を保障してもらえるなんて、管理管には感謝してる。ちょっとおかしいと思う面も、確かに有るけど」
「……反対…」
僕と反対だった。
サキヤの両親が憎い。
しかし僕の中では、サキヤを産んでくれたことに感じる感謝の気持ちの方が、勝っていた。
管理管が憎い。
確かに外の生活は外の生活で、苦しいだろう。しかし、束縛され切った生活に、反発心を時折抱いてしまうようになった。何故か。
何故僕たちは、この生活から抜け出すことができないのか。
食事なんか、とうに忘れてしまっていた。
サキヤが唇を噛み締めたのが、――やけに印象的だった。
この感情を抱くのは、いけない事……?
next...
+サン+
授業が終わった。
宿題の束を受け取る。
今日は土曜日で、明日は日曜日だ。ガッコウが休み。
休みの日は宿題をして、そしてまた月曜からのガッコウに備える。
僕は、そんな生活しか知らなかった。
+++
午後二時、家のベルが鳴った。
その無機質な音を鳴らして無機質なドアを開けてやってきたのは、サキヤだった。
「……サキヤ?」
突然の来訪に驚いて声がかすれてしまった。ガッコウではよく話をするし通信も頻繁に行っていたが、サキヤが家へやってくるなんて珍しかった。
ましてや事前の連絡無しでやってきたのは、これが初めてに違いない。
「どうしたの……? あ、入ってよ」
僕が玄関にスリッパを揃えて出すと、サキヤは小さく「おじゃまします」と言ってそれを履いた。
サキヤを自室に通して、僕はコーヒーの仕度をする。
配給の栄養配分されたコーヒーを、飲料加熱機で温める。
「おまたせ」
僕の部屋に戻ると、サキヤはベッドの淵に腰掛けたまま、じっと膝を正視していた。
「飲むだろ?」
ベッドから少し離れたテーブルにコーヒーを置くと、サキヤは少し笑ってベッドから立った。
「ぼく、配給の飲食物の中で、一番このコーヒーが好きだな」
一口飲んで、サキヤがぽつりと呟いた。
「そ…そう? もっと飲む? 温めてこようか」
ようやく言葉を発したサキヤにほっとして思わずそんなことを口走ると、サキヤは僕の顔をじっと見た後、苦笑した。
「いいよ、いいよ。一杯で充分」
「そうか。……このコーヒー、研究員が普通のコーヒーと変わらない味で栄養価を高くするのに結構時間費やした、ってこの間……」
僕が必死に言葉を繋いでいると、サキヤがクスと笑って「ごめん」と続けた。
「ヒダカ、今日は珍しく多弁だね」
…………。
自分でも、不自然だと思った。
「もしかして、気、遣ってくれたとか?」
苦笑するサキヤに、少し戸惑ってからこくりと頷く。
「元気、無いみたいだから……」
「ありがと。ごめんね」
すまなそうに俯くサキヤを見て、僕は酷く混乱してしまう。
多分、こういうシチュエーション、あまり無い。
+
サキヤが補充されてきたのはおよそ四年前の、初等四年の時だった。
補充当初彼は2クラスに居て、それから数ヶ月、1クラスに上がってくるまで顔も名前も知らなかった。
同じクラスになってからも、別に自己紹介の時間が設けられる訳でもないので交流は無かった。
ただ顔だけは「見たことが有る」程度で、教師との会話の中で補充生だと云うことも知った。
初等六年の時だった。
いつもより早くガッコウに着いた僕は、朝食代わりの配給ドリンクを忘れたので珍しく学食に足を運び、ドリンクを受け取った。
そのまま教室に上がらず学食のテーブルの上に参考書を広げてドリンクを飲んでいたら、その補充生がはす向かいに座った。
空いている席は他にも沢山――というか、人がまばらで閑散とした空間だったのに、彼は僕の傍に座った。
急の不自然な出来事で呆気に取られて思わず彼の顔をじっと見詰めていると、彼も僕を見詰めた。
そんな彼の第一声は、
「そんなものが朝ご飯なの?」
だった。
僕はますます呆気に取られて、「はぁ?」という声だけが口を吐いた。
彼の持っているトレーに目をやると白米と味噌汁と野菜炒めがのっていて、彼はそれをテーブルに置き、とても美味しそうに食べ始めた。
栄養なんて、ドリンクだけで充分だ。ゼリー状だから割と腹も膨れる。
それに朝食は大切だ。下手に自分で選んだ食事をして栄養バランスが崩れる方が怖い。
それでも僕はなぜだか彼に興味を持つようになってしまって、それから時々早めに登校しては学食に行くようになった。
僕が姿を見せると、彼は屈託の無い表情で笑った。
普段ここで生活していて、あまり見る表情ではない。
僕は徐々にそんな彼に慣れていき、会話を交わすようになった。名前も教え合った。
僕の前のサキヤはいつも穏やかで、いつも優しかった。
彼の言葉を押し付けがましく思ったことは無かったし、彼は僕を見下すような物言いもしなかった。
サキヤは管理官に認められただけあり、とても優秀だ。クラス落ちしたことは一度も無いし、彼が何か仕崩したところも見たことが無い。
解けなかった宿題を教えてもらったこともあった。
僕がクラス落ちした時も何も言わず、ただ一緒に勉強してくれた。
サキヤ自身はクラスなんて気にしないと思っているようだったけれど、僕がクラスを気にしていることを馬鹿にせず尊重してくれた。
でも、それ以外にも外から来た時の感想を聞いたこともあった。
思いついたことも色々と話している。
身にならない話なんて必要無いと思っていたけれど、僕は初めてそれを楽しいと感じて、そして友人というものを知った。
+
そんなサキヤの、滅多に無い沈んだ態度。
それはここへ来る前の話をする時だった。
今回もそれに関係があるのだろうか。
「サキヤ?」
もうすっかり飲み干してしまったコーヒーのカップを弄んでいるサキヤに、声をかけてみる。
それでもサキヤは顔を上げない。
仕方無い。
サキヤが今話したくないと思っているのなら、僕はそれを受け入れる。
いつもサキヤがそうしてくれていた。
僕はお代わりのコーヒーとビスケットを取りに、キッチンへ行く。確か配給のビスケットがあったはずだ。
シティの甘くないビスケットは、サキヤも好んで食べる。
カーテンが引かれて薄暗いダイニングでビスケットを探していると、急に足音がした。
びくっとして視線がずれたひょうしに、ビスケットが見付かる。
首だけで振り返ったらサキヤが立っていて、僕は彼にビスケットの箱を見せて「食べるか?」と問いかけようとした。
「……サキヤ?」
中途半端にビスケットの箱を掲げた格好で、僕は止まってしまっていた。
僕の背中に、サキヤが張り付いていた。
首に抱き付くみたいにして、力無く。
しばらくの後そのままするすると腕は離れていき、僕の足元に崩れ落ちる。
「サキヤ!」
ようやく身体ごと振り返り、急いでサキヤの肩に手をかけた。
「サキヤ?」
静かに問いかけて、うなだれた肩をゆっくりと起こす。
「ヒダカぁ……」
今にも泣き出しそうな表情で、サキヤはようやく僕に焦点を合わせる。
「どうした?」
サキヤがいつもしてくれるみたいに、できるだけ優しい声で促す。
彼は少しだけ唇を噛んで、それから、ようやく薄く唇を開いた。
「……クラス、落ちた」
そう告げる声は、酷く痛々しかった。
クラス落ち。
サキヤにとっては初めてのクラス落ち。
でも彼はいつもクラスにはこだわる様子を見せなかった。いつも自分の全力を出し切るだけで、無駄な意識をしていなかった。
想像もしなかった程の彼の取り乱し様に、僕はうろたえる。
僕がクラス落ちした時、サキヤはそれでも今までと同じ僕として扱ってくれた。
だから僕も同じ気持ちだ。
サキヤがクラス落ちしたからと云って彼の価値が無くなるとは思わないし、見損うつもりもない。そんな必要がないのだから。
でもサキヤ自身が、酷く落ち込んでいる。
多分、前にクラス落ちした時の僕よりも。
「ぼく、要らなくなるかもしれない……。いや、もう要らないんだ……」
「何、言って……」
僕が言い終わるよりも先に、彼は泣き崩れてしまった。
声を上げて、子どものように泣きじゃくる。
僕はどうすることも出来なくて、サキヤが一頻り泣き終わるまでただ彼の背中を撫でていただけだった。
+++
薄暗いダイニング。
僕らはソファに移動した。サキヤは僕の渡したタオルで涙を拭いながら、それでも上を向こうとしない。
僕はそんな彼の傍をそっと離れて、グラスにミネラルウォーターを汲んで戻った。
サキヤの手からタオルを取り、代わりにそのグラスを持たせる。
「飲んで?」
そう促すと、ようやく顔を上げて水を一口口にした。
唇の端から零れる水を親指で拭い、サキヤは小さく息を吐く。
「……ありがとう……少し、落ち着いた」
「そ、か……」
彼の手からグラスを取り、テーブルに置いた。
カツン、というガラス同士のぶつかる音が耳につく。
「突然ゴメン。押しかけて、みっともないところ見せて……」
微笑んで首を横に振ると、サキヤはほっとしたように力を抜いて再び泣き出した。
「クラス、落ちたのか?」
「うん……今日、前回の試験の結果発表でしょ?」
「あ」
今日からだったか。
クラス照会は毎回各自で行うことになっている。三日間、専用のサイトで公開されるのでアクセスし、自分のIDカードをリーダーに通すと成績とクラスが閲覧できるようになっている。
「昼食の時に思い出して、アクセスしてみたら……2クラスに落ちてた……」
やっぱりクラス落ちしてショックで取り乱したようだ。
「……クラスとか、気にしないと思ってたけど」
「うん、僕もそのつもりだった。でも実際クラス落ちしたのと、……ちょっと色々重なっちゃって、……」
途中で言葉が止まり、嗚咽が漏れる。
「……ぼく、要らなくなるかもしれないって……思ったら、急に怖くなって……」
「どこからそんな…」
「だってぼく、成績がいいからってこの街で生活させてもらってるんだから……成績が悪くなったら、きっと……」
「そんな……」
そんな馬鹿な。
外から補充と云うのは聞くけれど、その逆という話は聞いたことが無い。
ましてサキヤ程優秀なニンゲンを、おいそれとは手放さないだろう。
「何か、あった?」
何も無いのに、急にこんな風に取り乱すとは思えない。
きっと何かそう思う理由が……。
「あ」
そこで、ふと思い立った。
外の生活。
サキヤが編入するまでに暮らしていた外の生活。一緒に暮らしていたご両親。お金と引き換えにサキヤを手放した……って言ってたか……。
僕には何も出来ない。
何も出来ないけれど、サキヤを全部受け入れてあげたいと思う。受け入れたい。……僕の方こそ、彼が必要なのだから。
「ヒダカ……。ぼく、家族にも要らないって言われて管理管にまで要らないって言われたら、どうしたらいいんだろう……」
「要らなくなんか、ないって……」
そうだ。
僕は彼を必要としている。
でも、僕には何が出来る?
家族のように一緒に暮らして、大人のように子を養うことも出来ない。
管理管のように生活を保証することもできない。
僕はただ彼の存在を要するだけで、何も出来ない無力な人間だ。
「ヒダカ……ぼくのこと、必要? 要る?」
「必要だよ。凄く必要」
僕に色んな大切なことを教えてくれたのはサキヤなのだ。否、何も教えてくれなくとも損得勘定一切抜きでもサキヤは必要だ。
でも僕はサキヤに何が出来るだろう。
僕の健康のことを気遣ってくれたり、シティでの生活で知り得なかった色々なことや、感情までも教えてくれたサキヤ。
友人としての、サキヤ。
僕には何が出来る?
「ぼくの家族から、数ヶ月振りにメールが来たんだ。ぼくがシティに編入する前に生まれた妹が、ピアノを習い始めたって言って、ピアノを弾いてる動画で」
ぽつりぽつりと、サキヤが順序立てて話し始める。
「季節の挨拶程度しか寄越さないくせに、わざわざ妹の動画メールだよ? ぼく、妹の姿を見たのって二年振りで、正直本当に妹かどうかも判らなかった。でもそれを見ていたら無性に自分の存在価値なんてくだらないんだって思えてきて」
そのメールを見たすぐ後に、クラス照会をしたらしい。
気がついたら僕の家まで走ってきていて、そしてまた気がついたら泣き喚いていた……と、サキヤが恥ずかしそうに言う。
「ほんとに、ぼく、要らない人間だったら、どうしよう……」
サキヤがシティに来てくれたことに、僕は心から感謝する。
しかしサキヤにとって、シティに来たことは一種心の傷になっているのだ。
「ねぇ……ヒダカ、ぼくが外に一緒に行って欲しいって言ったら、ついてきてくれる?」
「え?」
外に、行く?
困惑して、返事を戸惑う。
「無駄かもしれないけど、家族のこと、見てみたいんだ……」
「う…ん……」
外に出て、サキヤの家族のところへ行って。
もし家族がサキヤのことを必要としていたら、きっとサキヤの不安は取り除かれる。
こんな風に泣かなくて済む。
……じゃあ、行くべきなのだ、きっと。
僕にできることなら何でもしたい。
でも、ふと自分勝手な不安が胸をかすめてしまった。
サキヤの家族が本当はサキヤに帰ってきて欲しいと思っていて、サキヤがもし外へ戻りたいと思ったら?
シティを離れてしまったら?
――そう思うと、居ても立ってもいられない。
それでも、……それでもやっぱり、家族はサキヤのことを必要としていると思うし、それをサキヤ本人が理解することが必要なんだと、思う。
どうなるか、わからない。
でも僕に出来るのはきっと、このくらいなのだ。ただついて行って、傍にいることしか出来ないけれど。
僕に出来ることなら、なんでもしたい。
「うん。行こう? サキヤの家族のところ」
自分自身にも言い聞かせるみたいに、はっきりと言う。
「ほんと?」
心配そうに俯いていたサキヤの顔が、ぱっと上がる。びっくりしたように、少しだけ頬を紅潮させて。
「ヒダカ、いいの?」
「うん。行こう」
next...
+ヨン+
外。
シティの外に出るのは、これが初めてだ。
外に出る許可は、あっさり下りた。サキヤの四年目にして初めての里帰りだからだ。頻繁になると許可も取りにくくなる。
サキヤが突然訪ねて来た日の、翌週の日曜日。
モバイルPCといくつかの身の回りの物だけをバッグに詰めて、洋服を着る。
シティ内ではあまり着ることの無いコートも、必要だとサキヤに説明されたのでクロゼットから引っ張り出す。
準備が整ったところで、玄関のベルが鳴った。
ドアを開けると、サキヤ。
「おはよう」
「うん、おはよう、ヒダカ」
サキヤは不安で顔を曇らせていた。
「大丈夫だよ」
根拠の無い僕の頼りないセリフに、それでもサキヤは表情を和らげてくれた。
「行こうか、サキヤ」
うん、としっかりと頷き、サキヤが歩き始める。僕もそれに続いた。
シティの最北。
シティと外を繋ぐゲートまでやってきた。
ドアに近付くと、シュウと音を立ててゆっくりと開く。中に入るとまた扉が有り、その扉は開いていた。部屋の向こうにまた扉が見える。
今開いている扉の隣に、カードリーダーが設置されていた。
『IDカードヲリードサセテクダサイ』
プログラムされた声が、スピーカーから流れる。
サキヤがIDカードを取りだし、スロットさせた。
『IDナンバー、イッチシマシタ』
シュウと音を立て、その向こう側の扉が開く。
二人で並んでドアをくぐった。
途端、扉は閉められた。
一つ先の部屋の扉を開いていき、通った扉はすぐに閉まってしまう仕組みのようだ。
次の部屋でも同様にカードを通す。扉が開く。
また次の部屋でも同様に次の扉が開き、僕らは同時に足を踏み出した。
途端、ビィビィと警告音が鳴り響く。
『ニンズウガイッチシマセン。ニンズウガイッチシマセン。スミヤカニタイシツシテクダサイ』
しまった。
タイミングがずれたか。
外へ出る許可が下りたのは、サキヤだけだった。
僕は許可が下りるどころか申請さえしていない。純血である僕に許可が下りないのは、目に見えていたからだ。
「走って、ヒダカ!」
僕がうろたえた瞬間、サキヤの声が飛ぶ。
「あ、ああ」
閉まりかけたドアを急いで通り越し、警告音の鳴り響く部屋を走り抜ける。
先刻カードで開けた扉が、最後の扉らしかった。向こう側に眩い太陽光が見える。
しかしその扉も警告音と共に閉じようとしていた。
全力で走る。
「くっそぉ……!」
走りながら肩から斜めにかけていたバッグを下ろし、扉目掛けて思い切り投げ付けた。
ガンッ!
閉まりかけていた扉にバッグがちょうど挟まるようになり、安全装置が働いて扉が再び全開する。
こう云った重要な施設の扉は、一度安全装置が働いたら次は最後まで閉まるように設計されている筈だ。
耳にまとわりつくような警告音を聞きながら、光に向かって全力で駆けぬけた。
半分ほど閉じかけた扉を、まず僕がくぐった。
「っ!」
眩しい太陽光が僕を突き刺して、一瞬視力が効かなくなる。
すぐに視力が回復しシティの方を振り返った。
サキヤがすぐそこまで来ていた。
「サキヤ!」
扉のすぐそこまで来ていたのに、サキヤの手からIDカードが滑り落ちてしまった。
ゆっくりと閉じていく扉。
左手後ろの方に落ちたIDカードを急いで拾い上げ再び態勢を戻した時には、もうほとんど扉は閉まりかけていた。
サキヤのスピードは、止まったことによって死んでしまっている。
「サキヤぁ!」
声を張り上げて、扉に手をかけ身を乗り出し、手を差し出す。
サキヤはそれを掴んだ。
全ての力を振り絞ってドアを押し、同時に手を引くと、サキヤがその勢いで地面に転がり込むように扉を潜り抜けた。
扉が閉まったのは、その直後だった。
バッグの中のモバイルPCが、ぐしゃりと音を立てて潰される。PCの硬さのお陰で安全装置が働いたのだろう。
緊張とか恐怖とか、そういう感情が綯交ぜになってしまっていて、しばらく動くことができなかった。何も考えられなかった。
こういうの、初めてだ。
心臓だけがばくばくといやに早く大きく打っている。
サキヤも同じように固まったまま、扉を見詰めていた。
「ヒ…ダカ……」
勢いで転がっていた僕たち二人は、サキヤの声をきっかけにようやくゆっくりと立ち上がる。
「いてて……」
転がった時に顔をすりむいたみたいだ。
「大丈夫? ごめんね、ぼくの所為で……」
「それより早く逃げよう」
「う……うん」
僕等は踵を返して、走り始めた。
少し走って、シティを振り返る。
ざぶん、と水の音がした。
「島……?」
シティは、海に浮かぶ島だった。
+++
ターミナルの裏の公園で、傷口を洗った。
「痛い? ……よね、傷だもん」
「大丈夫、大丈夫」
こんな傷、たいした事無い。
「大丈夫じゃないよ、怪我してるんだよ? 駄目だよちゃんとしないと。ほら、じっとしてて」
サキヤが僕の右の頬骨辺りに出来た傷に、バンソウコウを貼ってくれる。
そんなサキヤの言動に、何故か笑ってしまった。
「な……なに? ヒダカ。ぼく、何かおかしい?」
呆気に取られるサキヤに、首を横に振る。
なんだかサキヤらしくて、と笑いながら告げると、サキヤも笑い出した。
「そうだよね。沈んでるぼくなんてぼくらしくないしさ」
「いや、そういうつもりじゃ……」
そういうつもりではなかった。
いつも元気でいろとか、笑っていろとか、思ってない。
確かにそういうところがサキヤの長所だしいいなと思うけれど、だからと云ってそれを押し付けてサキヤが辛く感じるのは嫌だ。
「……そういうつもりじゃあなくて……」
でも、それを上手く伝えることができない。感情が上手く言葉に出来なくて、戸惑う。
「ヒダカ、ありがとう」
そんな焦る僕を見かねて、サキヤが再び笑ってくれた。
「でもさ、ヒダカは手がかかる子だから、ぼくがしっかりしないとね」
冗談めかして言う。
「ほら、お腹空いたでしょ。食事しよう?」
「あ、ドリンク……」
潰されたバッグの中だ。バッグ無き今、僕はもう何も持っていない。
「ほら、また配給のドリンク。駄目だって言ってるでしょ。ちゃんと噛んでご飯食べなきゃ」
サキヤがカバンを持って歩き始めた。
歩いて数分の所にある建物の中に入っていく。サキヤが、ここは銀行だと説明してくれた。
そこで通貨を下ろし、レストランで食事を摂る。
山のように有るメニューの中から、僕はサンドウィッチとコーヒーを頼んだ。
食事をしながらサキヤの家がどこにあるのか尋ねる。
「うーん。列車で三時間位かかると思う」
「そか。急がないと」
明日はまたガッコウだ。きちんと授業に出るためには、夜までには帰らなければならない。宿題も有る。
「じゃぁ、コレ食べたら、もう列車で移動しようか」
ナイフとフォークを器用に動かしながら、サキヤが微笑んだ。サキヤはマナーの成績も良い。
「うん」
僕はサンドウィッチを手に取った。
+++
列車の切符を購入し、車内に乗り込む。
窓から景色が流れていくのを僕が物珍しそうに眺めている反面、サキヤは俯いたままであまり口を開かない。
途中何度か乗り換えをして、約三時間後、目的の駅まで辿り着いた。
切符を駅員に渡し、外へ出る。
サキヤは少しそわそわと周りを見渡した。
「サキヤの家の近く?」
「うん。間違い無い。ここからバスに乗ってまた少し歩くけど」
駅前に有るバス停でバスが来るのを待ち、それに乗り込む。
バスを降りた頃には、少し日が傾きかけていた。
「サキヤの家?」
「……の、筈なんだけど……」
辿り着いた一戸建ての家屋の門には、『売家』の札が掲げてあった。
よくは見えないが、中に人が居る様子も無く殺伐としている。
引っ越したのだろうか。
「……あはは……」
酷く辛そうな表情で、乾いた笑い声。
「サキヤ?」
「あはは……はは……」
それも徐々に弱まり、ぺたんと膝を突き、道路に座り込んでしまった。
サキヤの家族は、サキヤに何の連絡も寄越さぬまま引っ越してしまった、と考えるのが妥当だろうか。
家族を見てみるというのは、家族が自分を必要としているかということが知りたいわけで、居ると思っていた場所に居なかったということは、……。
「サキヤ……」
言葉に詰まった。
同じように隣に座り込み、そっと背中に手を添える。
「もう……駄目だぁ……。あはは」
涙も流さず、サキヤはただ笑顔を貼りつけるだけだった。
+++
夜が訪れた。
コートが無かったらどうなってしまうんだろうか、と思う程、冬の夜は寒い。
こんな夜を過ごすのは、初めてだった。
公園のベンチ。
通りを大人たちが楽しそうに談笑しながら歩いて行くのを何組も見た。
大人が笑うところなんて、初めて見る。
外のニンゲンはあんな風にするんだなと単純に感心しながら、サキヤにも笑って欲しいなと思っていた。
サキヤは一言も発することなく、俯いたままで隣に座っている。
声を掛けよう、何か気の利いたセリフを……と考えあぐねてタイミングをみているうちに、何時間もの時間が経過した。
今晩はシティに帰られないかもしれない。
初めてガッコウを休むことになるかもしれないというのに、何故か不安も焦りも感じられない。
今頃シティではことがばれて問題になっているだろうか。
しかしそんな考えも酷く現実味が無く、目の前のサキヤの問題のほうがずっとリアリティがあった。
ピィッピィッ
「?」
サキヤのカバンの中から、突然の電子音。
はっとしたサキヤがごそごそとカバンを引っ掻き回し、PCを取り出す。
「ゴメン。アラームだった」
公園の時計は午後十時を指している。
「一応十時には寝る準備始めるようにしてるんだ。それで」
恥ずかしそうにアラームを切って、再びカバンの中にしまう。
ようやくサキヤが口を開いてくれた。僕は胸を撫で下ろしたい気分だった。
「サキヤっ、あの」
でも上手く言葉はつながらない。せっかくのきっかけだ。今を逃したら、また沈黙が続いてしまう。
「ゴメン、ヒダカ」
「……え?」
「折角あんなことまでして付いて来てもらったのにさ、無駄だった。ゴメン」
「そんな……」
首を思い切り横に振る。
辛いのはサキヤなのに。
「ヒダカ、そんな辛そうな表情しないで。ぼくなら全然平気だし。要らないと思われるぼくが悪いんだから」
「違うっ、サキヤは悪くないっ。要らなくないっ」
ありがと、とサキヤは短く言って柔らかく微笑んだ。
でも、全然笑えていない。
胸が痛い。
「きっと何かの間違い……そうだ、本当にあの家?」
「……間違いないよ」
僕の言葉に、首をゆるく振られた。
「ぼくの家族は、ぼくのことを置いて引越しした。これで全てだよ」
「ごめん、……ごめん……」
「どうしてヒダカが謝るの、ヒダカは少しも悪くないのに」
傍に居て、一緒にここまで来たのに、僕には何も出来ない。
よく解らない感情に胸を刺激されて、咽喉の奥が痛んだ。
なんだこれ……。
「ヒダカ、泣くことないよ……」
「……っ……」
僕は泣いていた。
何故涙が出るのか、僕自身にもよく解らない。
酷く咽喉が痛んで、目が熱い。
それでも僕は「ごめん」と、ただサキヤに言い続けることしかできなかった。
何も出来ない自分が情けない。
サキヤが悲しんでいるのか辛い。
そう思えば思う程、咽喉が痛む。
「ヒダカ……」
僕の背中を撫でながら、サキヤも声を出さずに泣き出してしまった。
+++
ドーム状の遊具の中で仮眠し朝方目が覚めたら、サキヤは既に起きていた。
「おはよう」
やはり目元は少し腫れていて、笑顔も無理しているように見えてしまう。
公園から出ると、再びサキヤの家の前。
「サキヤ……」
「うん。大丈夫。帰ったら、また一緒に勉強しよう」
にこりと笑う彼に、僕はただ頷くだけで応えた。
家に背を向け、一歩踏み出す。
その途端、遠くから子どもの声がした。
「おにいちゃーん!」
何気なく振り返ると、僕よりも早く振り返っていたサキヤが、目を見開いている。
そうしている隙にその子どもは僕たちのところへ走り寄ってきた。
「おにいちゃん。おにいちゃんだよね?」
あどけない高い声で、たどたどしい言葉を繋げる。
その言葉は、サキヤに向けられていた。
「……?」
サキヤの口から、小さな声がこぼれる。
「シイナ……?」
「おにいちゃん!」
ようやく僕らのところへ辿り着いたその子どもは、ぴょこんとサキヤに飛び付いた。
「もしかして……」
「…………多分、妹」
確かに四歳くらいだ。幼稚園の制服らしき洋服を着ている。
「どうして、こんなとこに。どうしてぼくのこと……」
サキヤは目の前のことが理解出来ないらしく、ぱくぱくと口を開く。
呆然とする僕ら二人を尻目に、その子はぱぁっと明るい表情でしゃべり始めた。
「おにいちゃん、シイナのピアノ、きいてくれるの?」
妹を目の前にして何も訊けないでいるサキヤの代わりに、僕は彼女と視線の高さを合わせた。
「シイナちゃん? どうしてお兄ちゃんのこと判るの?」
「おしゃしん、いつもみてるの」
「ここ、お家?」
売家になった家を指指す。
「うーうん。ここは、まえのおうち」
サキヤがぎゅっと手を握り締めた。
「……やっぱり、引越したんだ。……もういいよ、帰ろう、ヒダカ」
妹に背を向け、歩き始めてしまった。
「サキヤ……」
「いいよ、帰ろう」
「よくない。ちゃんと訊こう? ……シイナちゃん、どうして引っ越したか判る?」
そうまくし立てるように質問すると、彼女は人差し指の先を軽く咥えるようにして考え込んだ。
「うんとねぇ、ひろい、から」
「広いから?」
「うん。ママがね、パパとママとシイナだけだと、ひろすぎてイヤだって、いったの」
それはつまり。
「お兄ちゃんが居ないから?」
「うん。ひろいと、いっぱいいっぱい、さみしくなるからだって」
「サキヤ……」
声を掛けると、サキヤは僕たちから少し離れたところで俯いていた。
「ねぇ、おにいちゃん、かえってきたの? パパがネ、おにいちゃんはおべんきょうができるから、いいとこにいったんだよって、いってたヨ」
今度は僕が尋ねられてしまった。
「……それは……」
サキヤ次第だ。
サキヤは家族に必要とされている。
それを理解するのは当初の目的だった。サキヤはこれで、悲しい思いをしなくても済むのだ。
でも、……でも。
「サキヤ……」
サキヤはこのまま家族のもとへ帰ってしまうだろうか。
「シイナ」
サキヤが妹の肩に手をかけた。
「お兄ちゃんと会ったこと、パパとママには内緒だよ」
「え?」
急の約束に、思わず僕が先に反応してしまった。
シイナちゃんはゆっくりと首をかしげる。
「どうしてぇ?」
「お兄ちゃんはね、帰らない。パパが教えてくれたように、お兄ちゃん、いいところでお勉強してるから」
シイナちゃんは腑に落ちないと云った様に再び首をかしげた。
「ねえ、いいところって、どんなところ?」
「ヒミツ」
サキヤは意地悪をするように、にっこりと笑ってシイナちゃんの唇に人差し指をちょんと当てた。
彼女は大きな瞳を何度も瞬かせた。
「ねえ、どうしてシイナはここに居るの?」
「…………」
顔面蒼白といった感じで、シイナちゃんが俯く。
「……迷子?」
僕とサキヤで、顔を見合わせる。
「ようちえんばすに、のったの。そしたら、おうちがみえたの」
「それで抜け出してきたってことか……」
「幼稚園の名前、判る?」
「うん!」
元気に幼稚園の名前を言うシイナちゃんの頭を撫でて、サキヤはモバイルPCを取り出した。
ネットで検索にかけて場所を調べるつもりのようだ。
「サキヤ、新しい家じゃなくていいのか?」
だいたいの住所を聞いたら、きっと辿り着くことは出来るはずだ。
母親ならまだ家に居る確率も高かろう。
「……いいんだ。幼稚園に送るよ」
検索結果が表示される。
「行こうか、シイナ」
PCをしまい、シイナの手を繋ぐ。それから反対側の手を僕と繋ぐように言った。
僕とサキヤの間で嬉しそうにしているシイナちゃん。
歩く時にこういう風に手を繋ぐのは歩行の邪魔にならないか? と思ったけれど、何故か不思議と温かい気持ちになった。
シイナちゃんの速度に合わせて、ゆっくりと歩く。
「あ、ようちえん!」
二十分程歩いたところで、シイナちゃんは明るい声を上げた。
園庭からは子どもの声が聞こえてくる。あまりに喧しいので初めは喧嘩でもしているのかと思ったが、どうやら遊んでいるらしい。
「じゃあ、シイナ、お兄ちゃんとはここでお別れだよ」
幼稚園の手前で、サキヤは歩を止めてシイナちゃんの手を離した。
彼女は不安そうな表情で、サキヤを見上げている。
「……ばいばいなの?」
「そう。……元気でね、シイナ」
ベレー帽の頭を、そっと撫でてやる。
シイナちゃんは急に幼稚園用のカバンの中をごそごそとやりはじめた。
そして中から取り出したものを、サキヤに手渡す。
「これね、きのうようちえんで、せんせいとつくったの。おにいちゃんにあげる」
「……ありがとう」
「おにいちゃんにも」
とてとてとシイナちゃんが僕の方に走り寄り、同じように手を出してきた。
僕が手を出すと、シイナちゃんの手のひらから僕の手の中に、ころんと転がり込む。
シイナちゃんは満面の笑みを浮かべて走り出した。
「ありがとう、おにいちゃんたち」
一度門の前で振り返り、大きく手を振る。僕たちもそれに応えて、大きく手を振った。
シイナちゃんは子どもたちの歓声の中へ、溶け込んだ。
シイナちゃんに渡されたのは、細長いピンクのプラスティック容器とストローだった。
「シャボン玉……」
容器の蓋を開けて、中に詰まった水溶液にストローを漬ける。
ふうっと勢い良く息を吹き込むと、ストローの先から液が散ってしまっただけだった。
「あれ……」
うまくいかないな……と少し落ち込みながらサキヤの方を見ると、彼は上手に数多の球体を吹き出していた。
「うわ……サキヤ上手い」
僕たちを取り巻く淡い七色の球体にそっと指を触れると、それは当たり前のように弾けて消えてしまった。
日に照らされ、弾け散った後の霧状の水溶液がキラキラと輝く。
僕らはしばらくその光景を見入っていた。
「ヒダカ、帰ろうか……」
シャボン玉を吹く事を止め、サキヤはくるりと僕の方を向く。
サキヤの目的は、果たされた。
「でも……」
それでいいのだろうか。
サキヤは必要とされていた。それで、シティに帰って、サキヤは満足なのだろうか。
「いいんだよ」
言葉を繋げられないで居る僕の心を見透かしたように、サキヤは笑って言った。
「帰ろう」
と。
next...
+ゴ+
一週間。
一週間の間、僕はガッコウへも行けず外出することも許されず、サキヤと通信することさえも出来なかった。
監察処分を受け、四六時中見張られている生活。
そんな生活が一週間続いて、僕はようやく解放された。
登校してクラスに入ると、いの一番サキヤが飛んできた。
「ヒダカ!」
急いで席を立ち走り寄ってくるので、途中いくつも椅子や机にぶつかっていた。
「おはよう」
その姿が妙に可笑しくて笑いながら挨拶すると、サキヤは脱力したように僕を凝視した後溜息を吐いた。
「ヒダカ、なんだか余裕だね……」
「そんなことない」
外から戻ってきてから直ぐに連絡を絶たれていたのだ。サキヤと話したいことは色々あったし、気分もなんだかいつもと違った。
一週間も欠席を重ねた僕の登校と、騒ぎ立てるサキヤに、流石に視線が集まった。
普段は僕らのことなんか見向きもしないのに。
「学食、行かない?」
その視線に気付いたのか、サキヤが僕の制服の裾を引っ張って言った。
カバンを机の横にかけ、サキヤに続いてクラスを出る。
学食で、今日は初めて僕がサキヤの分まで注文した。
野菜入りのリゾットを口へ運ぶ。
なかなか美味しいなと思いながらサキヤの方を見ると、彼は少しも箸を進めていなかった。
「サキヤ、食べないのか?」
俯いたままのサキヤに問いかけると、首を横に振る。
一体どうしたのかと口を開こうとしたところで、サキヤはテーブルに手を突いて頭を深く下げた。
「ゴメン、ヒダカ」
呆気に取られてスプンを握ったままその様子を見詰めていると、ゆっくりとサキヤが頭を上げる。
「僕の所為で、ヒダカ、一週間も謹慎でおまけに監察なんて……気分悪かっただろう? それに、折角1クラスに上がったのに、2クラスに落とされて……」
「な…んだ。そんなこと」
土下座のようなことまでされて謝ってくるので、これから何が起こるのかと内心かなり焦ってしまっていた。
「そんなこと、じゃないよ……」
心底申し訳なさそうに、しゅんとしているサキヤに無理矢理箸を持たせる。
なんか今日の僕、いつものサキヤのようだなと思う。
「ヒ…ヒダカ?」
「ごめん、ちょっと可笑しくて」
僕、外に行ってから、少し変わったのかもしれない。
サキヤと一緒に居て得てきた物に、またプラスされたような気がする。
「クラスなら、次、一緒に上がればいいし」
「そうかもしれないけど……」
依然として申し訳なさそうな表情をしたままで、箸をぎゅっと握り締めている。
「サキヤの不安が取り除かれたら、それでいい。良かった」
そしてガッコウで再びサキヤと会うことが出来て、本当に良かった。
彼が家族に必要とされていて安心したのと同時に、彼がシティから去ってしまうのではないかという不安がさらに膨れ上がってしまっていた。
それでもサキヤは、帰ろうと言ってこの街へ戻ることを望んでくれたのだ。
「……ヒダカ、聞いてくれる?」
僕とは対照的に、思いつめたような表情でサキヤが言う。
「うん……何?」
また少しドキ、として、それを表に出さないようにしながらサキヤの言葉を促す。
「ゴメン。ぼく、最低だ……」
何を言い出すんだよ……と呆気に取られて何も言えないで居ると、サキヤは益々落ち込んだように俯いた。
「ゴメン、ヒダカがそんな風に思ってくれてると思うと、なかなか言い出せなくて。ずっと黙ってたんだ……」
振り絞るような声で言葉を繋ぐサキヤは、辛そうで痛々しい。
きゅうと僕の胸が痛んだ。
「なに……を?」
「ぼくが必要か確かめたいなんて、思ってなかった」
「ど…ういう、こと?」
「最初から、必要とされてないって決め付けてたんだ。ほんとはね、幸せそうにしてる家族を見たら、復讐しようと思ってた。無茶苦茶にしたいって思ってた」
「サキヤ……」
「ゴメン、ヒダカの気持ち踏みにじるみたいなこと……」
「そ…か……」
どんな気持ちだったんだろう。
僕に外へついてきてくれと告げた時、家族が引っ越してしまったと知った時、シイナちゃんを見た時、家族のことを聞いた時。
「復讐……出来た?」
出来たわけがない。
売家を見た時は酷く落ち込んでいたし、シイナちゃんと会った時は、立派なお兄ちゃんをしていた。
復讐とか、きっと頭からすっかり抜け落ちていて、必死だったように思う。
でもサキヤは、困ったようにちらっと僕の顔を見て、
「うん、ちょっと」
と続けた。
「え、そうなの?」
「シイナに、ぼくのこと言うなとか、いいところに居るんだとか言った」
それ…が、ちょっと実行した復讐?
「きっとシイナは隠せないよ。ぼくが来たことを言ってしまうと思う」
シイナちゃんが父親と母親に兄のことを告げたら。
きっとまたサキヤのことを鮮明に思い出してしまい、母親は余計に寂しくなるだろう。
そもそもシイナちゃんが、サキヤの写真を常日頃目にしている状況なのだ。
「ぼく、最低だ。ゴメン」
でも、でも寂しいのは家族だけじゃない。サキヤだって今までずっと辛い思いをしてきた。家族に捨てられたと思い、シティからのプレッシャーも感じながら。
そしてまた、罪悪感に押し潰されて。
「サキヤ、えらかった」
家族のことを恨む気持ちは肥大していた筈なのに。
「よく頑張った」
きっと滅茶苦茶にしようと思えば出来た筈だったのに、結局サキヤは何もしなかった。
精一杯の強がりを残すだけしか。
「サキヤは最低じゃない。謝ることない」
「ヒダカぁ……」
ぎゅっと瞑ったサキヤの目尻から、涙が零れる。
「ありがとう、サキヤ」
「それ、ぼくのセリフだと思うけど……」
手の甲で涙を拭いながら不思議そうに首をかしげるサキヤに、僕はもう一度、ありがとうと呟いた。
+++
僕はこの街で生まれた。
この街で育った。
この街で学習をし、自己の能力を生かし、いずれこの街の為になる仕事をするだろう。
それが正しいことなのか、間違ったことなのか。
僕には判らない。
正しいとか間違っているとか、そんなことを考えること自体、酷くくだらないと思っていた。
ただ全てが馬鹿馬鹿しいと思っていて、ガッコウもシティもニンゲンも、意味の無い、価値の無いものにしか思えなくて。
自分の感情すら、理解できなかった。
今は?
今は……。
僕には、シティには……価値があるのだろうか。
そもそも、この街――Lシティは何故生まれたのだろう。
四百平方キロメートル足らずの島で、外とは隔離された街。
一切の生活苦を取り除かれる代わりに、知能だけでニンゲンは判断され、優劣を決められる。
研究、開発、外の企業への助力……仕事は山のように有る。
財政ももちろん潤う。
が、それが目的か?
うっすらと知り得た外の生活と自分たちの生活にあまりに差が有りすぎて、理解できない。
僕たちの生活が普通だと捉えた時、外のニンゲンのしていることはあまりに愚かではなかろうか。
反対に外が普通だと捕らえると、僕たちは酷く意味がないことをやっているように思える。
僕たちは、一体何故上を目指しつづけるんだ?
僕たちはシティにとって、何なのだろう。
+++
「サキヤ……」
監察処分が終了して丁度一週間目の朝、通学途中にサキヤと出会った。
僕らは外へ出て以来、地下通路よりも地上から移動することが増えた。
こっちの方が気持ちいい。
「ヒダカ、おはよう」
サキヤがにこりと微笑む。
しかし僕の表情を覗きこんでから、少し表情を曇らせた。
「どうしたの? 元気、無い」
「元気無くはない。大丈夫」
「嘘。じゃあ、何か悩み事でもある?」
「……」
くだらないかもしれない、こんなことを考えるのは。
どうなるかわからない。
それでも、僕は決めてしまった。
「サキヤ、僕、管理タワーに行ってみようと思う」
サキヤは、何を言っているのか解らない、と云った様に首を小さくかしげて僕を見詰めた。
僕がそれ以上何も言わないでいると、少しずつ理解したようで、驚いた表情になる。
「それって……侵入するってこと?」
僕は少しためらった後、うん、と首を縦に一度振る。
「そ……か。じゃあ、ぼくも行く」
「え?」
「だって、ヒダカもぼくの為に外についてきてくれた。だからぼくも、ヒダカの迷惑にならないならついて行きたい」
優しい表情。
「迷惑なはず、無いだろ」
「良かった」
僕たちはロッカーにカバンを放り込んで、駆け出した。
答えは有るのか判らないけれど。
答えを、求めて。
next...
+ロク+
『シンニュウシャアリ、シンニュウシャアリ』
警告音が鳴り響き、赤い光が点滅する。
その中を潜り抜け、ようやく僕らが最奥の部屋に入ると、それらはぴたりと止んだ。
「……なんだ……? ここ……だよな?」
僕が独り言のように呟くと、部屋を見渡していたサキヤが「多分」と返事してくれる。
薄暗い部屋。
冷たい空気の部屋。
モニタパネルが半円を描くように壁に埋め尽くされ、様々に光を放っている。光源はそれだけだった。
暗い部屋の中でパネルはじっと見るには眩しすぎて、くらくらした。
「このモニタ、シティを映してる?」
ようやく目が慣れてきたのか、サキヤがそれらを見上げながら声を出す。
「……ほんとだ…。なんだよここ、誰も居ないのか?」
タワーの中には一切プレートが掲げられていないため、ここがどこか判断しかねる。管理関係だと云う、当たり前のことくらいしか解らない。
早まっていた鼓動がどうにか収まりかけた時、モニタの半円の中心で声がした。
「いらっしゃい」
逆光でよく見えなかったが、確かにそこには人影がある。
「誰だ!」
驚いた勢いで声を荒げると、小さな溜息とカチリと云うかすかな音が聞こえ、薄く部屋が照らされた。
モニタの前に立っていたのは、細身の女だった。
「誰だよ……」
「勝手に入ってきて、いきなり『誰だ』は失礼なんじゃないかしら。そんな風に教育されたわけじゃないでしょう?」
ひどく感情の読み取れない声。
外を見てきた後だと、それがLヒューマン独特だということがよく判る。
「貴方たちね、侵入者っていうのは」
何も言えないでいる僕たちに、一歩一歩ゆっくりと近付いてくる。
近くなるにつれ見えてくる彼女は、成人していないと思われる、場にそぐわないくらい若い女だった。
「いらっしゃい、よくここまで来たわね。あたしは管理官のミヤギよ」
「管理官!?」
管理官が居ることくらい解っていた。
それがこの街のニンゲンだと云うことも、当然だと思っていた。
しかし実際には管理官など見たこともなければ、どんなニンゲンなのか想像したことすらなかったのだ。
管理官という、言葉しか頭に無かった。
「若い……」
まさか、こんな若い女だとは思ってもみなかった。
「管理官だって歳をとるのだから、若い管理官に変わるのは当然でしょう? あたしは管理官を四年前に受け継いだわ」
距離が二メートル程までに縮んで、ミヤギは歩を止めた。
人工的なまでに整った顔つき。
頭の上の方で二つに結ってある、つやのある、黒く長いストレートヘア。
左右不対称な黒いスカートと、肘の部分から絞ってある袖の、白いブラウス。
そして、真っ赤なスカーフのようなネクタイが印象的だった。
「四年前には、あたしも今の貴方達と同い年だったわ。……ヒダカくんと、サキヤくん」
「僕たちの名前…!」
「当然でしょう? あたし、管理官よ? お望みなら、前回試験の成績を言い並べてあげましょうか」
「……結構です」
この若さにして、Lシティのトップを務める彼女だ。多分、全住民のデータが頭の中に入っているのだろう。
「ヒダカくん、貴方先週まで監察処分を受けていたでしょう? その上タワーに侵入するなんて、どうなるか解っていてやっているのかしら」
「ヒダカは悪くないです。ぼくが無理を言ったんだから」
サキヤが一歩踏み出すみたいにして主張するのを、そっと腕を引いてたしなめた。
「僕が行きたくて行ったんだ」
「ヒダカ……」
少し沈黙が走ると、ミヤギが口を開く。
「そういうの、サキヤくんに教えてもらったの? それとも外で見てきたの?」
僕が呆然とミヤギを見ていると、「付焼刃では、そんな風にはいかないわよね」と一人納得したように呟いた。
「この話はもういいわ。それより、貴方達がどうしてここに侵入したのか、理由を話してもらいましょうか。大丈夫よ、事を荒立てたくないからガードシステムの方は手を打っておいたから」
既に侵入しておいて厚かましいかもしれないが、それを聞いて少しほっとした。
話も出来ないまま追い出されたのでは、意味が無い。
「この街の存在理由を……僕たちがここに居る必要性が知りたくて」
ここへくれば、何か判るような気がした。
何を知りたいのかさえ曖昧な僕らの、答えがあるような気が。
「愚問ね」
表情色一つ変えることなく、腕を組んだまま僕らを見る。
その姿は酷く冷たくて、何故か悲しみを帯びて見えた。
「じゃあ、貴方たちが生きている理由は?何?」
「僕たちが、生きてる理由?」
「あたしは管理官として仕事をする為に生きているわ。いいえ、生かされているの、……この街にね……」
管理官として生きないあたしには、価値なんてないの。――ミヤギがかすれた声でそう続ける。
「貴方は、はっきり言える? 自分の目的」
「Lヒューマンとして、上を目指す……こと……?」
「じゃあ、この街から出て行ったニンゲンには、価値がないの?」
「……」
「あたしを置いて出て行ったあの人には、価値なんて、……無いのね」
ミヤギの初めて見せた表情は、遠くを見るような、そんな悲しい目だった。
何故か胸がきゅうとなる。
「あたしも直に価値が無くなるわ。管理官じゃなくなるから」
「まだ若いじゃないか……。もっと優秀な管理官が居るというのか?」
「違うわ」
その声は、たった一言なのに様々な感情を含んで聞こえた。
「新しいシステムが開発されているの。管理官としてのプログラムが全て組み込まれた、ね」
「管理官と成り代わる、システム?」
「そう」
ニンゲンではなくて、システム。コンピュータ。
歳を取るニンゲンではなく、交代しなければならないニンゲンではなく、永久にシステムするコンピュータ。
感情を持つことなく、正しいと認識させられたことのみを正しいと判断する。
「ヒダカくんのお母さんが参加している開発よ」
「……」
普段母親と会話をする機会がないので、母親がどこへ行きどんな仕事をしているのか知らなかった。
否、母親は話さないだろう。
きっと極秘に行われているプロジェクトに違いない。
「そんな話を、一般人のぼくたちにしてもいいんですか?」
サキヤが僕と同様のことを感じたようで、ミヤギにそう言う。
「タワーに侵入してきた貴方たちに窘められるとはね」
ふふっと可笑しそうに笑われた。
それもそうか……。
「それが完成したらね、あたしはお払い箱。あと何年かかるかは判らないわ。でも、いずれなんの価値もない、ただの小娘になるの」
人に成り代わるシステム。
もしそれが完成したら、本当にミヤギには価値が無くなるのか?
「でも管理官は、記憶力が……」
サキヤが言いかけるのを、ミヤギは首を振ることで止めさせた。
「そんなこと、コンピュータなら容易いことよ。あたしである必要が無い。……価値が無くなることは、避けられない事なのよ」
「でも……でも本当に必要無い人間なんて居ない」
サキヤが必死に訴える。
同じことを考えていたサキヤにだからこそ言えるセリフなんだろう。
人間が必要だとか必要でないとか、何故考えなければならないんだ?
何なんだ、この街は。
何故人間がそれを考えるまでに追い詰められなければならない?
「何故……一体この街は……」
「何故この街が存在するのか……、教えてあげましょうか」
「え……」
知りたかった。
何故この街が存在し、僕たちが存在するのか。それを知りたくてここまで来た。
それをミヤギ、管理官本人の口から教えてくれるというのか。
信じていいのか少し戸惑いサキヤの方を見ると、サキヤは心配そうに僕を見ていた。
何も言葉を交わすこと無く、ただ互いに頷き合う。
「聞きます」
「ふふっ、ずいぶん素直に信じるのね」
そう教育されたものね、と小さくミヤギが呟いて、俯く。
「この街は、政府が公式に建設した街よ。外へ出た時に見たでしょう? 人工的に作られた島なの」
「あ…ああ……」
人工的に作られた島。
「いわば、ここはこの国の陰の中枢。国の為にここは機能してるの。いえ、まだ試験段階ですけどね」
……政府が建設した、国の為の?
ミヤギがゆっくりと振り返る。彼女の視線の先には、幾多のモニタ。
「あたしたちは、その歯車。いつ消えても問題の無い、シャボン玉みたいなものよ」
モニタに映るもの全て、国の為。
研究も開発も、僕たちさえも。
僕たちは、計画の一部として生きている――生かされているのか?
その事実について、疑問は……生まれないのだろうか。
「ねえ、何故だか判る? この街に、補充のニンゲンが入ってくる、本当の理由」
ミヤギが僕たちに背中を向けて問った。
ちらりとサキヤの方に目をやると、サキヤは少しだけ首をかしげて上目遣いで口を開いた。
「ニンゲンが、足りないから?」
「そうよ? でも、何故足りなくなるか、わかる?」
くるりと再びこちらに向き直り、無表情を保って言う。ふわりと髪の毛が揺れ、甘い香が漂った。
今度は僕が口を開く。
「子どもを産むのが、無駄だと感じるから……?」
「いいえ、子どもを産むのは義務よ。DNAを繋ぐのだから。現に二十五歳以上で子どもを持っていない人間は居ないわ」
「じゃあ……」
言葉に詰まった。
大人の数が足りてないのか?
「……思い当たるようね。流石純血のLヒューマンだわ」
「煩い」
「何故子どもの数と大人の数が見合わないのか。解るわよね? ……街を出て行くのよ、大人になる前に」
唇を噛み締めるミヤギが妙に感情を伴ったような気がして、胸がちくりとした。
「……大学期に……?」
沈黙が流れる。
管理官室の機械音だけが、低く耳に届く。パネルが煌々と光を放ち、シティのあちらこちらの情報を映し出す。
それが妙に無機質に思えた。
眉をひそめて目を伏せていたミヤギが、そっと瞼を開ける。
「ええ……。そうよ」
大学期に、初めて外へ出る。
こことは違う現実。
今までの自分と、周りの違い。
「気付いてしまうの。他の世界があるということに。そして、感情を知る」
僕は純血と言っても、祖父が外からの補充だ。
ただ、生まれながらにしてLヒューマンだと云うことに過ぎない。
「外のニンゲンは厄介よ。あたしたちに、感情を教えるの。……補充のニンゲンもね」
自嘲するような低い声で、呟く。
僕とサキヤは少しだけ目を見合って、ぎゅっと手を握り締めた。
「外のニンゲンなんて、補充しなければいいのよ。でもあたしは補充者を診断して迎え入れる。国の為の計画として、この街を完成させなければならないから」
街を構成するために必要なニンゲン。
でも、同時に厄介とも云えるニンゲン。
「だから、いくら優秀でも大人は補充しないわ。大人は自己を持ちすぎているから、子どもだけ。ガッコウに通わせて、慣らしていくの」
next...
自己。
ガッコウ。
Lシティ。
「そもそも大学期に外へ出さなければいいのよ。何も知らなければ、何も疑問を持たずに生きていくことが出来る」
「じゃあ何故……」
「一つの試練みたいなものかしら。外のニンゲンと同じ大学へ通って彼らよりも上だと実感し、またシティへ戻ってきてこそ本当にこの計画の成功と言えるわ。……うまくいかないものよね。もう延々と試験段階を抜け出せていないのだから」
何十年、否、何百年続いただろう、この街は。
そしてこれからどれだけ続けば、政府の求める『完成された街』になるのか。
「正直なところヒダカくん、貴方には随分期待していたのよ。純血だし、他の子よりも感情が薄くて、きちんと結果も出せていたから……。サキヤくんも初めはまるで純血Lヒューマンみたいにしていたから、大丈夫だと思ったんだけどね……」
でも僕たちは、互いに出会い、感情を持ってしまった。
それはこの街にとって、ミヤギにとって、プラスにはならなかったのだろう。
「あたしだって、……感情を知ってるわ」
誰でも持ち得る。
知らないだけで、本当は当たり前の感情たち。
笑ったり、楽しんだり。
……愛したり。
「人間って、そんな簡単なものじゃ、ないのよね」
だから完成しないのか、この計画は。
知能がいくら高くとも、所詮僕らは人間なのだ。
「でもね、あたしは管理官なの」
自分を突き放すみたいな。自分に言い聞かせるみたいな。
「おかしなものよね。あたしは管理官でいることでしか価値を得られないことを知っていて焦っている反面、管理官であることを否定したいなんて」
トップでいる自分。
いずれその大役を降りなければならない自分。
ミヤギは自分の立場を理解して、感情を押し殺して……。
酷く、痛い。
「ねえ、あたし間違ってるかしら……」
僕とサキヤは、ぎゅっと手を握り締めた。
何故、感情を受け入れることができないのだろう。
こんなの、間違ってる。
間違ってるのはミヤギじゃない、僕たちじゃない。
――コノ街ダロウ……?
「ミヤギは……間違ってなんかない」
上手く言葉に出来たら、どんなにいいだろうと思う。
「そういうの、当たり前だと思う……」
僕の思うことは、伝わるのだろうか。
僕がそれ以上言葉を繋げられず俯くと、サキヤがそっと口を開いた。
「きっと、管理官じゃなくなったらもっとよく見えますよ、自分の感情」
「でも、もう遅いわ。あの人は、もうあたしの傍には居ないから」
ミヤギは両手のひらをぎゅっと、感情を殺すように握り締めた。
ミヤギの大切に思っていた人は、ミヤギを置いてシティを去ってしまったのだろうか。
「必要とされないことが、こんなに辛いことだとは思わなかったわ……。いっそ、感情なんて無くなってしまえばいいのに」
感情なんて……。
感情なんて。
そんなに意味の無いことなのだろうか。
噛み合わなくて、愚かしいことなのだろうか。
否、そんな筈がない。
「そんなこと……」
僕の中の感情が、言葉が、堰を切ったように溢れてきた。
「そんなこと無い。ミヤギは誰かを必要と思ったことが有るんだろう? たとえその人が傍に居なくたって……」
ああ、頭の中がぐちゃぐちゃになる。
言いたいことは山のように有る。
「自分が必要とする人が、自分を必要としてくれる人とは限らないかもしれない。でも、誰かしら必ず必要としてくれる人が居る。その人を自分が必要とするかしないかは、自分次第じゃないのか」
自分を必要とするのが一人とは限らない。
サキヤだって、僕にも家族にも必要とされてる。
「他人が必要としているという自信が持てないのなら、自分で必要とすればいいじゃないか」
「な……そんな馬鹿なこと……」
「だって、それで必要無いって決め付けてたら、いつか本当に必要とされた時に、それさえも否定してしまうことになる」
言葉を外に吐き出しながら、僕はいつの間にか泣いていた。
涙は熱くて、そしてすぐに冷たくなる。
サキヤが僕の背中をそっと撫でてくれ、僕は制服の袖で涙を拭った。
「ミヤギは自分でも解ってるんだ。管理官であることは大切かもしれないけど、ミヤギには管理官として以外にも、絶対に存在価値が有る」
僕がミヤギをまっすぐに見据えると、彼女はぺたんと床に崩れた。
「……ありがとう。あたし、誰かに……誰か一人でもいいから、そう言って欲しかったのかもしれないわ」
ミヤギが、声と一緒に一筋の涙を流した。
「貴方達にも、それぞれ価値があるのよね。……どうするの? これから。この街を出て行く?」
「そしたら、どうなる?」
しばらく俯いていたミヤギは、そっと立ち上がりスカートの裾を整えた。
「どうにもならないわよ。お望みならばIDを削除するわ。まあ、残しておいても結構ですけど」
「出て行かない」
「え?」
突如発せられた僕の声に、ミヤギが珍しく表情を崩した。
「僕は、この街に残る」
「……それで、いいの?」
決めたんだ、僕は。
それが正しいのか、間違っているのか。そんなんことは判らない。
でも僕は少しだけ。
ほんの少しだけ、変わったと思う。
結局、狭い視野の中でしか生きてなくて、外どころかシティさえも見渡せてはいなかった。
シティにも、色々な感情が溢れている。
それを僕は知らなかった。
歯車として正しかった僕がそれを知ってしまうのは、シティとしては喜ばしくないことかもしれないけれど。
「判らない。それでも、今はここに居ると決めた」
僕はたくさんのことを学んだから。
「……そう。好きにするといいわ」
溜息のような声。しかし彼女は踵を返す瞬間、微笑んだように見えた。
「一ついいことを教えてあげる」
カツカツと靴を鳴らしながら歩くミヤギがふと歩を止め、振り返った。
「ヒダカくんのご両親ね、感情を人に伝えるのは酷く苦手な人達だけど、貴方、試験管ベイビィじゃないのよ」
薄暗い空間の中で、ミヤギは今度こそ柔らかい表情で笑った。
「貴方は、愛されて生まれてきたの」
お帰りはあちらよ、と再び僕らに背を向けて、ドアを開ける。
「ミヤギ……ありがとう」
「ありがとうございます」
僕たちの言葉に彼女が振りかえることは無かった。
「それはこっちのセリフだわ」
ありがとう。
消え入るようなほんの小さな声で、ミヤギが言葉を紡いだ。
僕たちはミヤギの背中にもう一度礼を言い、そのドアをくぐる。
侵入したときに鳴っていた警告音も赤い光もすっかり止んでいて、まるで何事も無かったかのような静寂を持っていた。
「帰ろうか、サキヤ」
「うん、帰ろう」
手を繋いで歩く。温かい気持ちになれるから。
帰ろう。
何が正しいのかは判らないけれど、間違っているのかもしれないけれど、元の生活へ。
僕たちの街へ、ガッコウへ。
+++
がちゃりとドアが開き、母親が帰宅した。
普段と変わらぬ乱れの無いウェーブの髪の毛。灰色のスーツ。
靴を脱ぐその背中に、僕は言葉を投げかけた。
「お帰り、お母さん」
+シュウマク+
初めて上ったガッコウの屋上から、シイナちゃんにもらったシャボン玉を飛ばす。
サキヤに教わり、随分上手く飛ばせるようになった。
「シャボン玉、か……」
「どうしたの? ヒダカ」
飛んでいくシャボン玉を眺めながら、ふと思い出した。
「ミヤギがさ、僕たちはシャボン玉みたいなものだって言ったなぁと思って」
「言ってたね」
言い得て妙だ、と思った。
今だって何も状況は変わっていないのだ。
「いいじゃない、シャボン玉。キレイだよ」
ふう、とサキヤがいくつものシャボン玉を作る。
「そう、だよな」
例え僕らが政府の歯車になり得る多くのニンゲンの中の一人でも、僕は僕であり続けるし、サキヤはサキヤであり続ける。
そこに意味が有るのか無いのかは……いつか決めれば良いことだ。
決められる時が、来たら。
「いつかは弾けて消えてしまうかもしれないけど、透明だけど、ちゃんと存在してる」
サキヤが言い終わるとすぐに、ふぅっとまたシャボン玉を飛ばした。
「ここにあるよ、ぼくたちの存在理由」
夕日に照らされて、サキヤの笑顔はとても眩しい。
「ここに居てくれて、ありがとう、サキヤ」
「ありがとう、ヒダカ」
何もない空間。
それは温かくもなり得る。
Fin
読んでくださった方、ありがとうございました。
コピぺしてて、6章がありえないくらい改行無くて笑えました。
これ絶対誰も読めないって!とか思いながらも無理矢理アップ。
なんとも言いがたい作品でスミマセン。
どこに投稿するつもりだったんだよ、みたいな。
登場人物の名前をみんな苗字ぽいカタカナ名にしようとしたら、
段々ネタに困り、『シイナ』は物凄い悩んだ末決めた名前です。
『ヒダカ』と『サキヤ』はお気に入りvv
もはやこれ以上のコメントすら思いつかない。
++今更キャラ紹介(と言うか整理)++
ヒダカ
:主人公。14才。純血のLヒューマン。
:喋ることが酷く苦手。でもサキヤと出会って、多少多弁になった。
:人に言われるままの性格。食事も衣服も、全て与えられた通り。
サキヤ
:初等4年の時に外から補充された。ミヤギが最初に選んだ補充。
:編入当初は親に捨てられたという思いから心を閉ざす。が、数年後変化有り。
:基本的に世話焼き。妹にジェラシーを感じるが、本当は可愛いと思っている。
ミヤギ
:14の時に管理官に抜擢された天才少女。
:16の時好きだった人が大学へ行き、そのまま行方知れずになる。
:本質的には人間味が有り、洋服やメイクも自分で選んでいる。
シイナ
:サキヤの実妹。サキヤが編入する数ヶ月前に生まれた。
:両親がシイナにかかりきりだった最中サキヤの編入が決まった。
:IQなどは極一般的。シティ編入は無いと思われる。
ヒダカパパ&ママ
:恋愛結婚。両者とも純血Lヒューマンで口下手。
:パパさんは薬品開発部、ママさんは管理システム開発部勤務。
こんな感じです。
テレビのチャンネルまわして 何度も何度も天気予報を見る。
明日は 晴れ。
何度も何度も確認するけど 当然どこのチャンネルも同じ予報。
あーあ。
雨が降ったら きみと一つのカサに入れるのに。
だから今日も僕は わずかな数字に期待してみる。
+++
これを数日前に書いて今打ち込んでたら、なんと明日の予報が降水確率10%だったー!(笑)
でも管理人、出掛ける時の雨は好きじゃないので「晴れろ!晴れろ!」と念じるタイプです。相合傘て濡れるしサ。。。
昇降口に行ったら、オレの靴が下駄箱の下に置いてあった。 「……新手のイジメか?」 不審に思いながら、上履きをしまうために下駄箱の扉を開ける。 視線は、床に置かれたオレのスニーカーに向けていたから、本当に『それ』は突然で。 ビックリした。 黒い物がいくつも、スニーカーめがけて落ちてきた。 え? は? 何、これ。 しゃがみこんで拾い上げたら、それは個包装された小さなチョコレート。 チョコレート。 下駄箱の中を覗いたら、同じチョコがぎゅうぎゅう詰めに入っていた。 オレの靴は、このチョコレートの大群に居場所を追いやられたらしい。 多分って云うか、絶対あの人。 絶対、あの人に違いなくて。 物凄く嬉しくて、でもイヤガラセみたいなこの仕打ちに、苦笑する。 全部のチョコレートをカバンに移したら、カバンがいっぱいになってしまった。 カラッポになった下駄箱には、やっぱり手紙も何もなくて。 そんなとこも、あの人らしい。 一日早いチョコレート。 全然素直じゃない。 そんなトコが、たまらなく可愛いんだけど。 +++ SSと表記すべきかどうか悩んだんですが、今回は無しの方向で。(適当) 明日はバレンタインですから。一日フライングで。 ちょっと夢見すぎだろうか。こんな風だったらたまらなく可愛いんだけど!とか思いながら書きました。(誰がとか訊かないお約束) ホワイトデーは3倍返しです。
ぐるぐる ぐるぐる
真っ白な包帯を きみに巻き付ける。
ぐるぐる ぐるぐる
痛みも 悲しみも 歪みも 全部僕が治してあげるから。
ぐるぐる ぐるぐる
その瞳に 何も映らないように。僕だけを 感じていられるように。
ぐるぐる ぐるぐる
――真っ白な包帯を きみに 巻き付ける。
傷が癒えた時 きみが何処かへ行ってしまうと 解っていても。
今だけでも 僕の傍に居て欲しいから。
ぐるぐる ぐるぐる
きみを 包帯で。
| 2004年02月11日(水) |
『午前一時』(SS) |
夏休み、午前一時。
部屋の隅に置いてある靴を履き、窓から家を出た。
暗くて静かで澄んだ空気の中、僕は走る。
「お待たせ」
神社の境内で、彼は僕があげた線香花火をしていた。
境内に取り付けられた古い蛍光灯。ろうそくの、小さな明かり。
「一緒に、花火しようよ」
「うん」
僕は彼から線香花火を一束受け取り、二人向き合って火を点ける。
「夏休み……もうすぐ終わるね…」
「そうだね。生活のリズム、元に戻すのが大変じゃない? 昼間は暑いし」
僕たちが深夜一時に逢うようになって、確かに生活リズムは乱れっぱなしだ。
ラジオ体操なんて、もう何日も出ていない。
学校が始まったら先生に怒られる。
「でも、今が楽しいから……僕はいいや」
線香花火の束をほどきながら、僕は小さく言葉を流す。
彼は安心したように笑みを浮かべた。
ゆるい風が吹き、ろうそくの火がゆれた。僕はもう一度、線香花火に火を点ける。
「しあわせって…云うのかな」
「しあわせ?」
「ん」
「……僕も」
ささいな幸せだけれど、これが今の僕にとって最上の幸せ。
夏休みはもうすぐ、終わってしまうのだけれど。
「――ぼく、やっぱり夏が一番好きだな。この時間、すごく好きだ」
少しうつむきながら言う彼に、僕はうなずくことで返事した。
何も言えないけれど、これが僕たちの時間。
テレビを見ることや遊びに行くことより、なにより大切に思う日課。
彼はふうっと息を吹きかけて、ろうそくを消した。かわりに蛍光の懐中電灯を灯す。
「そろそろ、宿題にしようか?」
夏休みの前に出された、たくさんの宿題。僕はいつもここで、それを見てもらっていた。
「うん。じゃあ今日は算数」
斜め掛けバッグの中から算数の宿題を取り出して、広げる。
社の縁に並んで寝転がる。
「あ……雨…」
ぽた、と宿題に水がつく。続けて、ぱらぱらと降り出した。久しぶりの雨。
「中に入ろう」
彼は蛍光灯を消して、僕の手を引いて社の戸を開けた。
真っ暗な空間。
格子の隙間から外を眺める。
雨の所為で、少し肌寒い。
夜明け前ようやく雨は上がり、外は明るくなった。
やがて、近所の公園からラジオ体操の歌が聞こえてくる。
「ラジオ体操、始まっちゃったね」
「平気。もう、父さんも母さんも会社に行ってるよ」
「…夏休み、終わるね」
「うん」
僕がうなずいて彼の方を向くと、もう彼の姿は消えていた。
「…また……明日の一時に、来るね」
格子戸を開けて外に出る。
夏休みはもうすぐ、終わってしまうけれど。
――了
+後書き+
始まって間もないのに、早くも昔の作品引っ張り出してきました。初出は18だか19の頃。
コピペアップ。手直しはウェブ向けに改行増やしただけ。
文章一切いじってません。(直せよ!)
近所に『午前五時』という花屋が有って(午前五時がバラが一番良く香る時間らしい)、
『午前○時』ていいなー。そんなタイトルの話書きたいなーと思って書きました(笑)。
手をつないだ。
他の誰にも見付からないように。 手をつないだ。
この手は僕のなんだっていう、ささやかな主張。 耳元でささやいた。
他の誰にも聞こえないように。 耳元でささやいた。
僕ときみしか居ないこの空間で、大切なきみに伝えたいこと。
ほっぺた触ったら、ぺしりとはたかれた。
顔のぞき込んだら、耳まで赤くしてにらまれた。
ああもう。
ぜんぜんかわいい。
そんなカオ見れるなら、オレ、アホでいいです。
きみの思いは受け取りました。
きみの痛みは、僕が貰います。
僕の置いてゆくものは、何も有りません。
『終わり』が悲しいんじゃなくて、きみと『出会えた』ことへの感謝。
+++
アバ終わっちゃった…記念。と言ったら殴りますか。そうですか。
全くそうは読み取れないかもしれないけども、それでも何か書きたかったんで。
一年間の幸福をありがとう。
僕ときみの直線距離。
このまま真っ直ぐきみには辿り着けない。
遠回りなんてしたくないのに、何故だか真っ直ぐ進めなくて。
近付いているつもりだけど、結局平行線。。。
意気地なしの僕を、
きみは笑うだろうか。
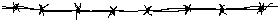 キミの声が、ちくりとボクの胸に突き刺さる。
そこから先に、ボクは入ることを許されない。
錆びて、朽ち果てて、その有刺鉄線が外れてしまうまで
ボクは、空気になろう。
| 2004年02月05日(木) |
『たっぷりの あい』 |
ふよふよ
ふよふよ
水の中でゆれる 赤いドレープ
きみが金魚だったらいいのにな
そしたら ガラスの金魚鉢に たっぷりの水を注ぎ込んで
毎日きみを見ていられるのに
風力発電のプロペラが回るのをただじっと眺めていたら、ひらひらと舞う蝶が視界に入った。
大きな黒い羽を青空に映わせ、上へ下へとラインが変動する。
何も無い――雲ひとつ無い青空に、一点の黒。
黒。
空と比べたらほんの、ほんの小さなその黒に。
僕は、魅入られた。
プロペラでなく、その黒をじっと目で追う。
プロペラは、もう視界からすっかり外れてしまっていた。
ひらり。
ひらり。
その蝶に誘われるようにして、僕は無意識のうちに立ち上がる。
一歩、二歩。踏み出したところで、ざぶん、波の音が耳に届いた。
風が有る。
風力発電のプロペラは相変わらずくるくるとまわっているだろう。
しかしもうそんなことに気など向けていられなかった。
ただ、ただ黒い蝶を追う。
自らの羽ばたき、そして強い風を受け、不安定に空を泳ぎ続ける。
ひらひら。
視線と足が、とり付かれたようにその動きを追う。
ふらふら。
追い続けることしか、頭に無かった。――出来なかった。
ざぶん、一際大きな波の音。
蝶は、海へ向かって羽ばたいていた。視界の青が、空から海へと変わる。
空も海もあまりに大きくて、蝶は、あまりにも小さくて。
ようやく、馬鹿馬鹿しさを覚えた。
ふっと息を吐いた瞬間。
ざぶん。
また一際大きな波が押し寄せ、岸壁に打ち付けられた海水が白く散った。
そして。
突風に吹かれて下降した黒い蝶が――波に呑まれた。
波に、呑まれた。
馬鹿馬鹿しくなった。
押しては退く、白い波を眺める。
僕は、眼下に広がる海に、全てを捨てることにした。
波にさらわれて海に沈んでしまったあの黒い蝶のように。
全部さらわれて、呑み込まれて、深く深く、光の届かないところへ沈んでしまえばいい。
希望も。
絶望も。
未来も。
過去も。
全部。全部捨てよう。
この手に残るのは、馬鹿馬鹿しい『今』だけでいい。
全部捨てた。
目を開けた。
胸の中にあった漆黒は、あの蝶のように波に呑まれてしまった。
あのプロペラのように回る、単純な今現在だけがこの手に有る。
何故だか、涙がこぼれた。
了
+後書き+
まだ詩のストックあるんですが、今日仕事中に書いた(殴)SSを。
ただ風力発電のプロペラが有る風景を書きたかっただけ。そこから広げました。(うわ適当…!)
暗さ漂う話でスミマセン。
| 2004年02月03日(火) |
『にぎりこぶし 1コぶん』 |
手をのばせば届きそうで。
でもそれは許されなくて。
僕は ぎゅっと手を握りしめる。
この にぎりこぶし1コぶんの きみへの想い。
きみへの、想い。
やり場の無いこの気持ちに 名前を付けることが 酷く怖い
形を持ってしまう前に
涙が零れてしまう前に
僕は 笑った
空は抜けるような青で でも 太陽は見えなくて
胸がきしんだ
神さま 僕に 声をください
|